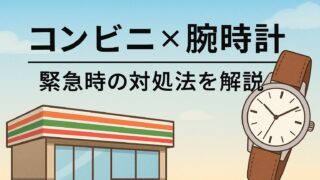「荷物を送りたいけど、わざわざ営業所まで行くのは面倒」——そんな時に便利なのが、コンビニからの宅配便発送です。
コンビニなら24時間営業の店舗も多く、仕事帰りや休日でも気軽に利用できます。
この記事では、ヤマト運輸と日本郵便のサービスを取り扱うコンビニを比較しながら、それぞれの発送手順や注意点をわかりやすく解説します。
コンビニで宅配便を送る前に知っておきたい基本情報
コンビニから宅配便を送る流れは下図になります。
【STEP 1】荷物を梱包する
↓
【STEP 2】対応しているコンビニを選ぶ
(ヤマト→セブン/ファミマ、日本郵便→ローソン/ミニストップ)
↓
【STEP 3】送り状を準備する(店頭 or スマホ)
↓
【STEP 4】レジで提出し料金を支払う
↓
【STEP 5】控えを受け取って完了
対応している宅配業者とコンビニの組み合わせ
| コンビニ | 対応宅配業者 | 主なサービス |
|---|---|---|
| セブンイレブン | ヤマト運輸 | 宅急便、宅急便コンパクト、ネコポス |
| ファミリーマート | ヤマト運輸 | 宅急便、宅急便コンパクト、ネコポス |
| ローソン | 日本郵便 | ゆうパック、スマートレター、レターパック |
| ミニストップ | 日本郵便 | ゆうパック、スマートレター、レターパック |
取り扱い可能なサービスは店舗によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
発送可能な荷物のサイズと重量の制限
- ヤマト運輸(宅急便):縦・横・高さの合計が160cm以内で、かつ重量が25kgまでの荷物に対応しています。これにより、一般的なダンボール箱であればほとんどの荷物が発送可能です。
- 日本郵便(ゆうパック):3辺の合計が170cm以内、かつ25kg以下の荷物が対象です。こちらも家庭用の荷物や小規模な引っ越し用品の発送などに広く利用されています。
いずれも、コンビニでの取り扱いに適したサイズや重さであり、規定を超える大型・重量物は営業所へ持ち込む必要があります。
特に、レジカウンターのスペースや保管場所に限りがあるため、可能な限りコンパクトに梱包することが推奨されます。
コンビニから送る場合は、持ち運びやすく、スムーズに受付できるような大きさ・重さを意識すると、店員とのやりとりや手続きもスムーズに進みます。
また、サイズオーバーによりその場で受け付けてもらえないケースもあるため、事前にメジャーで計測しておくと安心です。
ヤマト運輸の宅配便をコンビニから送る方法
セブンイレブンでの発送手順
- 店頭にあるヤマトの伝票を入手します。店内の専用ラックやカウンター付近に設置されていることが多いです。
- 伝票に必要事項(宛先・差出人・品名など)を記入します。スマホアプリ「クロネコメンバーズ」を使えば、宛名入力や支払いも事前に完了でき、QRコードでの発行も可能です。
- 荷物をしっかりと梱包し、伝票またはQRコードと一緒にレジへ持参します。レジで荷物の受付と伝票処理を行ってくれます。
- 支払い方法を選びます。現金のほか、電子マネー(nanacoなど)やクレジットカードに対応している店舗もあります。支払いが完了すると控えが渡され、発送が完了します。
ファミリーマートでの発送手順
ファミマでは「マルチコピー機」と「Famiポート」が使えます。どちらの端末も、店内に設置されていて直感的に操作できる設計になっています。
- スマホアプリで送り状を発行し、QRコードを表示します。これは事前に準備しておくとスムーズです。
- 店内のマルチコピー機でQRコードを読み取り、送り状を印刷します。端末の指示に従って操作するだけで簡単に印刷できます。
- レジで荷物と印刷した送り状を一緒に渡して発送手続きを行います。ここで支払いも可能です。
Famiポートを使用する場合も基本的な流れは同様で、QRコードを読み取ってレシートタイプの控えをレジに持っていくことで対応可能です。
スマホを使った送り状の作成方法
ヤマト運輸の「宅急便をスマホで送る」サービスを利用すれば、紙の伝票不要で簡単に手続きができます。
荷物の情報や宛先をスマホで入力しておくことで、店舗での作業が格段に短縮されます。
- アプリで宛先や発送内容を入力します。事前登録しておけば繰り返し使う際にも便利です。
- QRコードを生成し、スクリーンショットを取っておくと安心です。
- コンビニのマルチコピー機またはFamiポート端末でQRコードを読み取ると、送り状が印刷されます。
スマホから手軽に発送できるため、非接触・非対面でのやりとりを希望する方にもおすすめです。
また、アプリ経由の発送では割引が適用されることもあり、コスト面でもメリットがあります。
日本郵便の宅配便をコンビニから送る方法
ローソンでのゆうパックの発送手順
- 店頭のLoppi端末で必要な発送情報を入力します。差出人・宛先の住所や品名などを画面の指示に従って入力します。あるいは、事前にスマホアプリでQRコードを発行しておくと、端末での入力が不要になります。
- 入力が完了すると、Loppi端末から送り状(シール形式の伝票)が発行されます。それをレジに持参します。
- 荷物を梱包した状態でレジに持って行き、発行済みの送り状と一緒に提出します。ここで送料の支払いも行い、発送手続きが完了します。
ローソンではゆうパックだけでなく、スマートレターやレターパックなどの日本郵便が提供する定額発送サービスも取り扱っています。
これらは事前に購入しておくと、窓口での手続きが省けるため便利です。
ミニストップでのゆうパックの発送手順
ローソンと同様に、ミニストップでも日本郵便のゆうパックサービスを利用できます。
Loppi端末と同様の端末が設置されており、操作方法もほぼ同じです。スマホでQRコードを発行する方法にも対応しており、若干の機種差はあるものの、基本的な流れは共通です。
また、ミニストップでもスマートレターやレターパックの取り扱いがあります。
これにより、急ぎの書類や小型の荷物も気軽に送ることができ、ビジネス利用にも適しています。
スマートレターやレターパックの利用方法
- スマートレター:全国一律料金180円で、25cm×17cm×2cm以内、重さ1kgまでの軽量な郵便物に対応しており、ポスト投函が可能です。
- レターパック:全国一律370円(ライト)または520円(プラス)。ライトはポスト投函可能で厚さ3cm以内、プラスは対面での手渡し配達が特徴です。
これらのサービスはあらかじめ郵便局やコンビニで購入しておき、宛名や差出人を記入すればすぐに利用できます。
荷物が比較的小さく、追跡番号を付けたい場合にも便利で、多くの利用者に支持されています。
コンビニで宅配便を送る際の注意点とQ&A
発送できない荷物の種類
- 現金、貴金属、高価な電子機器(保険未加入の場合)
- 危険物、可燃物、生もの
- 大型で規定サイズを超える荷物
発送前にコンビニ店員に相談するか、公式サイトで確認するのが確実です。
支払い方法と料金の確認
- 支払いは現金・クレジットカード・電子マネーが利用可能(店舗により異なる)
- 料金は荷物のサイズと配送先によって変動
- アプリを使うと割引になるケースもある
よくある質問とその回答
Q:宅配便は24時間いつでも出せるの?
A:基本的には可能ですが、店舗によって受付時間に制限がある場合もあります。
とくに深夜帯や早朝の時間帯はスタッフが少ないため、一時的に受付を中止しているケースもあります。
荷物の受付時間については、事前に店舗へ電話などで確認しておくと安心です。
Q:コンビニで送り状はもらえる?
A:はい。伝票は店頭で無料でもらえます。専用のラックに設置されている場合が多く、必要な伝票を自分で選んで持ち帰ることも可能です。
また、スマホアプリと併用することで、QRコードでの受付にも対応しており、非接触での手続きもスムーズに行えます。
Q:クール便や着払いも使える?
A:店舗によっては対応していますが、冷蔵設備の有無などにより異なります。
たとえば、夏場の冷蔵庫容量に限りがある場合や、一部の店舗ではクール便を取り扱っていないこともあります。
着払いについては、基本的に対応していますが、伝票の種類が異なるため、事前に店員に確認してから記入するとスムーズです。
まとめ
コンビニから宅配便を送ることで、時間や場所にとらわれず手軽に荷物を発送できます。
ヤマト運輸と日本郵便で対応しているサービスや手順は異なりますが、それぞれに便利な点があります。
本記事で紹介した手順や注意点を参考に、目的に合った方法でスムーズに発送してみましょう。